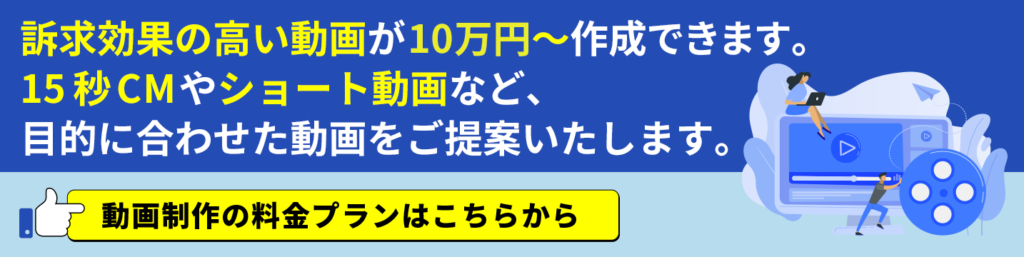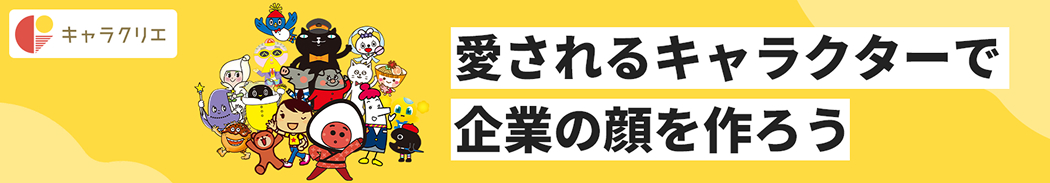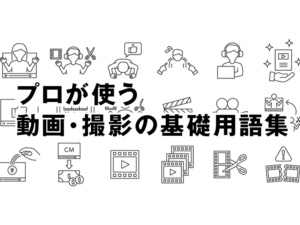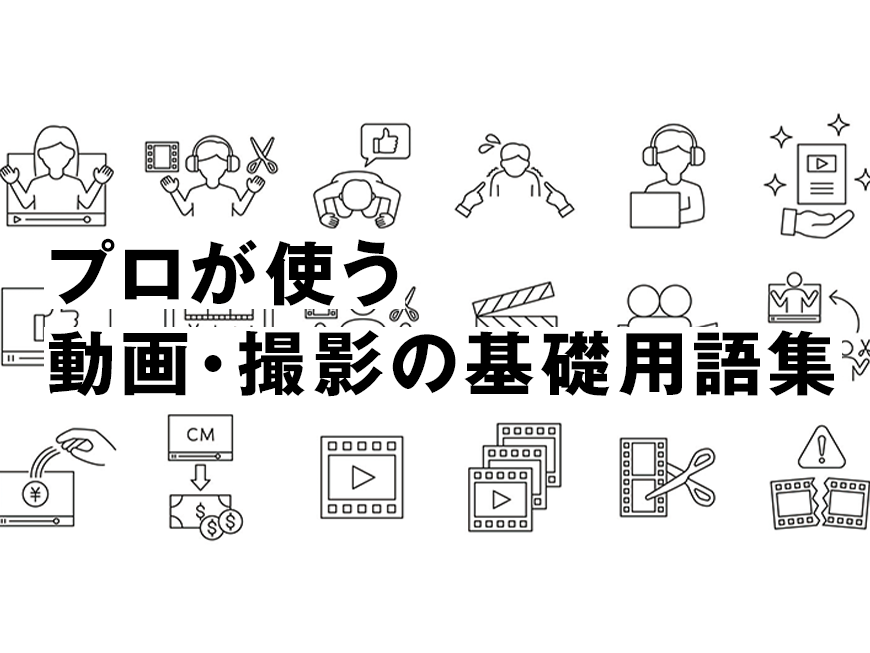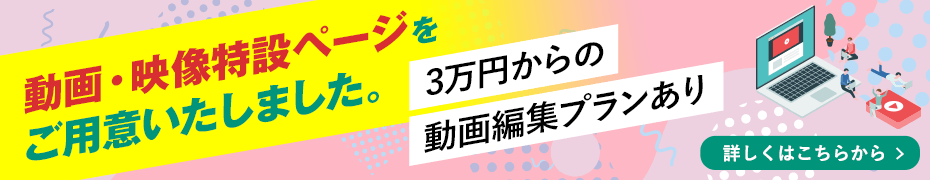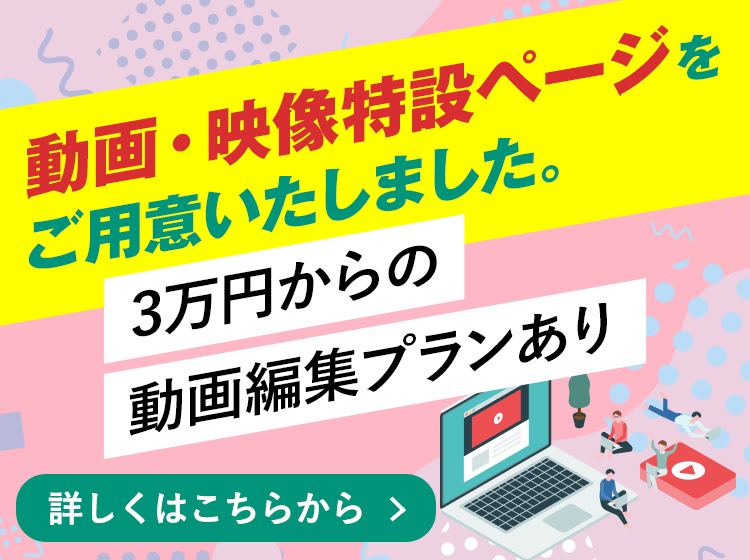展示会で数多の来場者の足を止め、自社のブースへと惹きつける「展示会動画」。これは、貴社のビジネスチャンスを最大化するための、極めて強力なツールです。
しかし、ただ映像を流すだけでは、その他多くのブースに埋もれてしまいます。既存の動画をそのまま流用しても、来場者の心には響きません。展示会動画は、歩きながら数秒で判断するという来場者特有の視聴意図を捉える必要があるからです。
「以前作った動画を使い回せばコストがかからない」
「そもそも動画に割く予算がない」
そうした考えも無理はありません。
しかし、展示会の目的に合わない動画を流用するのは、せっかくの製品やサービスの魅力が伝わらないばかりか、来場者の関心を惹きつけるという本来の目的も果たせません。結果として、貴重な商談の機会を逃してしまうことになりかねないのです。
本記事では、展示会ならではの動画の作り方について、企画の立て方から具体的な制作フロー、さらには展示会を成功に導くための「活用」までを網羅的に解説します。
この記事を参考に、目的を達成するための効果的な動画を作成し、貴社の展示会を成功に導きましょう。
【関連記事】
>展示会で動画が必要な理由はこれ!来場者を魅了する動画制作のコツも紹介
>展示会動画で差がつく!映像の展示方法と来場者を呼び込むブース設計
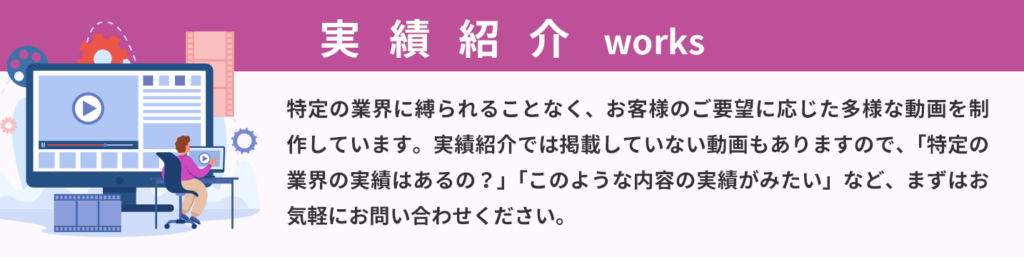
目次
1.展示会動画制作の目的と役割

展示会での動画活用は、来場者の興味を引きつけ、ブースへの滞在時間を延ばす上で非常に効果的です。しかし、ただ動画を流すだけではその効果は半減してしまいます。
多くの出展者が目を引くために工夫を凝らした動画制作を行っているため、効果的に活用するためには計画的かつ戦略的なアプローチが必要となるのです。
展示会で自社ブース前を通る来場者の足を止め、製品やサービスに興味を持ってもらい、商談に繋げるための動画でなければなりません。
その展示会動画の役割は、以下3つと言えるでしょう。
・認知度の向上
動画は視覚的に訴える力が強く、出展者のブランドを印象づけるのに役立ちます。
・製品やサービスの詳細な紹介
実際の動きや使用シーンを映像で紹介することで、文字や静止画では伝えきれない情報を提供できます。
・集客効果の向上
魅力的な映像があれば、足を止めてもらいやすく、集客につながります。
2.【5ステップ】展示会動画の作り方
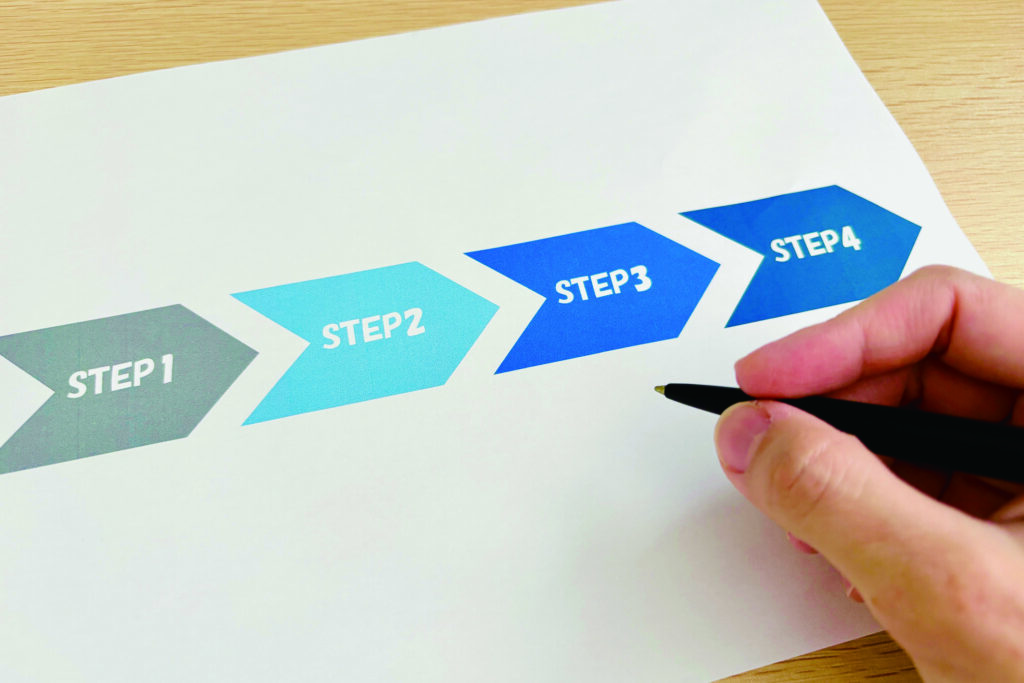
それでは、具体的に展示会動画はどのような手順で作っていくのでしょうか。ここでは、企画から完成までの基本的な制作フローを5つのステップに分けて解説します。
ここで注意したいことは、他の利用シーンで使われる動画とは考え方や作り方が違うということです。展示会ならではの状況を考えて作っていくことが重要となります。
Step1 目的とターゲットの明確化
動画制作において最も重要なのが、この最初のステップです。動画制作における核となる部分と言っていいでしょう。
・目的(ゴール)の設定
何のために動画を作るのかを具体的に定義します。「製品の認知度向上」「ブースへの集客数◯%アップ」「商談獲得数◯件」など、具体的な目標(KGI/KPI)を立てましょう。
・ターゲットの設定
誰に、何を伝えたいのかを明確にします。「情報収集段階の若手担当者」「導入を検討している決裁者」など、ターゲットの役職や課題、興味関心を具体的にイメージすることで、動画のトーン&マナーや盛り込むべき内容が決まります。
Step2 企画・シナリオ(絵コンテ)の作成
目的とターゲットが固まったら、動画の設計図となる構成とシナリオを考えます。展示会動画は、「不特定多数の来場者の足を止め、ブースに惹きつけること」が重要な役割です。Web動画のようにじっくり見てもらうのではなく、数秒で興味を引くインパクトが最優先で企画されなければならないのです。
・コンセプトの設計
まず「何を伝えたいのか」というコンセプトを明確にすることが重要です。コンセプトが曖昧だと、動画が単なる情報の羅列になりがちで、観客にインパクトを与えることができません。
・伝えたいメッセージ
ターゲットに最も伝えたい核心的なメッセージは何かを選定します。あれこれとメッセージを羅列するのではなく、できるだけ少なく短いメッセージを作成しましょう。
・構成の決定
「課題提起 → 解決策の提示 → 具体的な製品紹介 → 導入事例 → 行動喚起(CTA)」といった、ストーリーの骨格を組み立てます。展示会動画は冒頭の数秒で惹きつけることが重要なので、インパクトのある映像から始めるのが定石です。
また、展示会場は雑踏音が多い場所です。「音が聞こえない」という前提で、ナレーションやBGMに頼らず、大きなテロップ(字幕)や視覚的に分かりやすいアニメーションだけで内容が完全に伝わるように構成・編集する必要があります。
・シナリオ・絵コンテの作成
構成が決まったら、シーンごとの映像、ナレーション、テロップ、BGMなどを具体的に書き出した「絵コンテ」を作成します。
Step3 撮影・素材の準備
絵コンテが完成したら、いよいよ動画制作に必要な映像や素材を準備します。
・実写撮影
ブースの大型モニターでの放映を想定し、高解像度での制作が必須です。スマートフォンでの視聴が中心のSNS動画などとは異なり、遠くから見ても映像が粗くならないクオリティが求められるので、撮影が必要な場合はプロのカメラマンに依頼することをおすすめします。
・アニメーション・CG制作
複雑な仕組みや目に見えない概念を分かりやすく伝えるのに有効です。専門的な技術が必要なため、動画・映像制作会社に依頼するのが一般的です。
・既存素材の活用
映像や写真、イラストなど自社で所有しているものがあれば、その素材を使って展示会動画をつくることは可能です。著作権などもあるので、再度利用する場合は注意が必要です。
Step4 編集作業(テロップ・BGM・ナレーション)
撮影・準備した素材を、絵コンテに沿って繋ぎ合わせていく工程です。
・編集
撮影した映像をカットしたり繋いだりします。アニメーションの場合は動きをつけていきます。
・テロップ
展示会場は騒がしいため、音無しでも内容が伝わるようにテロップは必須です。重要なキーワードが瞬時に伝わるよう、フォントサイズや色、表示時間を工夫します。
・BGM・効果音
映像の雰囲気を演出し、視聴者の感情に訴えかけます。企業のブランドイメージに合った選曲が重要です。「音」は聞こえない場合が多いですが、展示会後の活用を考えるとBGMなどはつけておくことをおすすめします。
・ナレーション
プロのナレーターに依頼することで、聞き取りやすく、説得力のある動画に仕上がります。最近では音声生成AIを活用する動画も増えてきています。
Step5 試写と修正・納品
編集が一通り完了したら、関係者で試写を行い、最終チェックをします。修正が完了すれば、動画は完成です。様々なメディアで活用できる形式で書き出し(エンコード)を行います。
・チェック項目
冒頭のインパクト(目的の達成度確認)、テロップの視認性、ノイズや音ズレ、動画の長さ、誤字脱字などをチェックしましょう。
3.【目的別】効果を最大化する展示会動画の作り方のポイント

展示会動画にもさまざまな目的があり、その目的によって作り方が違ってきます。動画の世界観や伝え方、表現の仕方はもちろん、テロップの出し方や、ナレーションの声色など細部にいたるまで目的に応じた作り方が必要になります。
ここでは代表的な3つの展示会動画をタイプ別にわけ、それぞれ制作のポイントをご紹介します。
コンセプトムービー
コンセプトムービーとは、企業や商品の理念や想いなど、抽象的な概念を映像と物語で伝え、最終的には視聴者の行動を促すことを目的とする動画です。
ブースのメインモニターで放映することで、来場者の足を止め、惹きつける「アイキャッチ」の役割を果たし、集客を担います。製品のスペックではなく、その背景にある理念や世界観を伝えることで、競合他社との差別化を図り、共感を促すことができます。
| 長さ | 映像 | 内容 | 作成のポイント! | |
| コンセプトムービー | 30秒〜1分程度の短尺。 | 視覚的なインパクトが重要!ダイナミックな映像や演出が効果的。 | 詳細な説明はNG!開発にかけた思いなど、視聴者の共感を得るようなストーリー。 | 来場者の足を止めるために、冒頭の3秒が勝負!意外性のある映像やキャッチーなテロップから始めましょう。 |
さらに読む:ブランディング動画とは?
製品・サービス紹介動画
製品・サービス紹介動画は展示会で最も多い種類です。機能やメリットを伝え来場者の理解を促し、商談を円滑にします。ブース前のメインモニターで放映する方法もありますが、例えば、製品に興味を持ってブースの中に入ってきてくれた来場者に向けて見せる方法もあります。
| 長さ | 映像 | 内容 | 作成のポイント! | |
| 製品・サービス紹介動画 | 1分〜3分程度 | 実物などがある場合は、必ず撮影を!無形商材の場合は、アニメーションなどで分かりやすく表現します。※展示会に合わせて開発している企業も多く、動画制作に間に合わない場合があります。その場合は、3DCGなどで表現することがあります。 | 「何ができる商品なのか」「どのような課題を解決できるのか」「他社製品と何が違うのか」などを説明します。 | 来場者に直感的に伝えなければなりません。誰でもすぐに理解できる表現や言葉選びが重要です。ブース前で放映する場合は、冒頭にインパクトを! |
導入事例・お客様の声動画
信頼と共感を獲得し、導入を検討している来場者の背中を押す、クロージングの役割を担う動画です。この動画は、不特定多数の方へ向けたものというより、ブース内で関心を示されたお客様に、商談を補足する目的で個別にご覧いただくためのものです。
| 長さ | 映像 | 内容 | 作成のポイント! | |
| 導入事例・お客様の声動画 | 2〜5分程度 | インタビュー動画がメイン。単調になりがちなので、カット割りやテロップの出し方など工夫が必要です。 | 「導入前の課題」「導入の決め手」「導入後の効果」などを語ってもらいます。第三者のリアルな声は説得力を持ちます。 | 嘘っぽくなってしまうため、作り込みすぎないことが重要!お客様へのインタビューも自然体で喋ってもらうようにしましょう。 |
4.展示会出展後の動画活用戦略

これまで解説してきたように、展示会動画には、他の動画とは異なる特有の制作ポイントがあります。
しかしながら、展示会用に制作した動画を一度きりの利用で終わらせるのは非常にもったいないです。展示会動画の費用対効果を高めるには、会期中だけでなく終了後の活用まで見据えることが重要です。二次利用を前提に企画することで、コストパフォーマンスに優れた活用が可能となります。
限定公開コンテンツのための再編集
展示会で放映した動画を再編集して、来場できなかった取引先やステークホルダーに提供することで継続的な関係構築に繋げます。
さらに、予算があれば、展示会で紹介しきれなかった詳細な機能解説や技術者インタビューなどの動画を別途制作したり、展示会出展の裏側を撮影した動画(BTS動画)を公開したりなど、展示会ならではのコンテンツを作成するのも有効です。
お礼メールへの活用
展示会後、獲得したリードに対してお礼メールを送る際に、展示会で放映した動画のリンクを記載することで、記憶が新しいうちに再度製品の魅力を伝え、内容のリマインドを促します。
来場者は数多くのブースを訪れるため、一つひとつの製品を記憶し続けるのは困難です。インパクトのある動画は、来場者の記憶に残ることで、展示会後のお礼メールで「あの製品の会社だ」と改めて思い出してもらうという効果が期待できます。
SNSでの事前・事後報告
企業のPR活動にSNSの活用は不可欠です。展示会前の告知動画から展示会後のお礼や報告まで、自社のSNSアカウントを運用しているのであれば、積極的に活用していきましょう。
SNSで投稿する際には、展示会での動画を短尺に再編集して各プラットフォームに対応できる作り方が必要となります。
さらに読む:SNSで顧客とつながる!
営業資料への活用
商談用やブース前のアイキャッチとして展示会で活用した動画は、そのまま強力な営業ツールになります。商品の概要や基本説明を動画に任せることで、営業担当者は顧客との対話やヒアリングといった、より本質的な業務に集中できるのです。
まとめ:展示会の成果は動画の「作り方」で決まる!
展示会を成功に導く動画制作のポイントを解説しましたが、いかがでしたでしょうか。展示会動画の制作知識は、自社・外注を問わずプロジェクトを円滑に進めるために不可欠です。
特に動画制作を外注する際には、担当者が制作の流れを理解していることで、制作会社へ的確に要望を伝え、提案内容を正しく評価し、手戻りの少ない進行が期待できます。
さらに展示会動画は作って終わりではなく、展示会後の二次活用まで見据えて制作することで、その価値を最大限に高めることができます。
ぜひ本記事を参考に、来場者の心を動かす展示会動画を作り上げ、貴社の展示会を単なる「出会いの場」から「成果を生み出す場」へと変えていきましょう。
バドインターナショナルでは、展示会動画の制作のみではなく、展示会ブースの企画・デザインから設計、運営までトータルでプロデュースいたします。「効果を最大化する展示会動画を作りたい」「動画だけではなく、展示会全体をプロデュースしてほしい」などといったご要望も大歓迎です。お気軽にお問い合わせください。