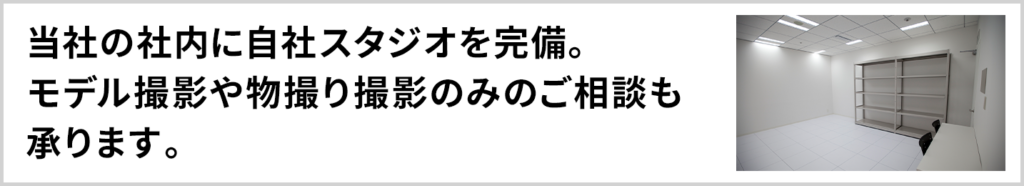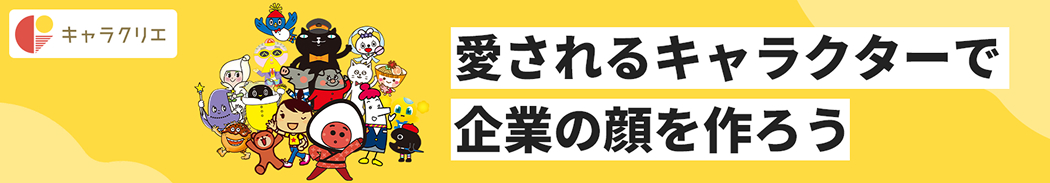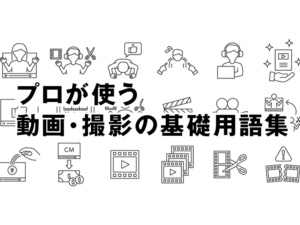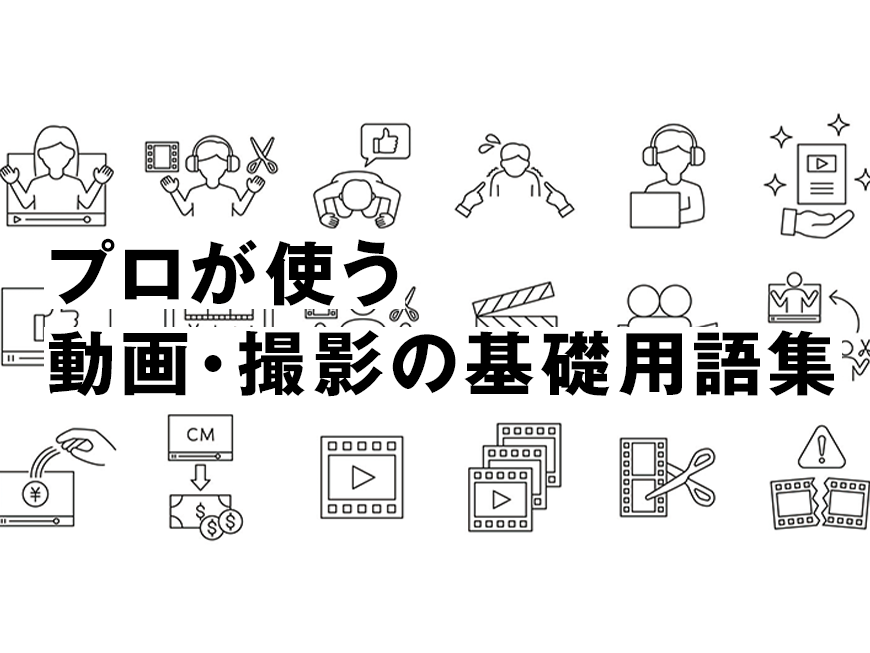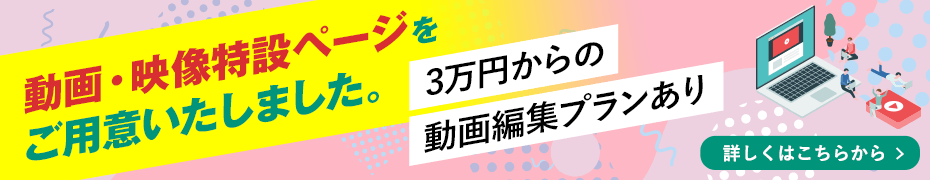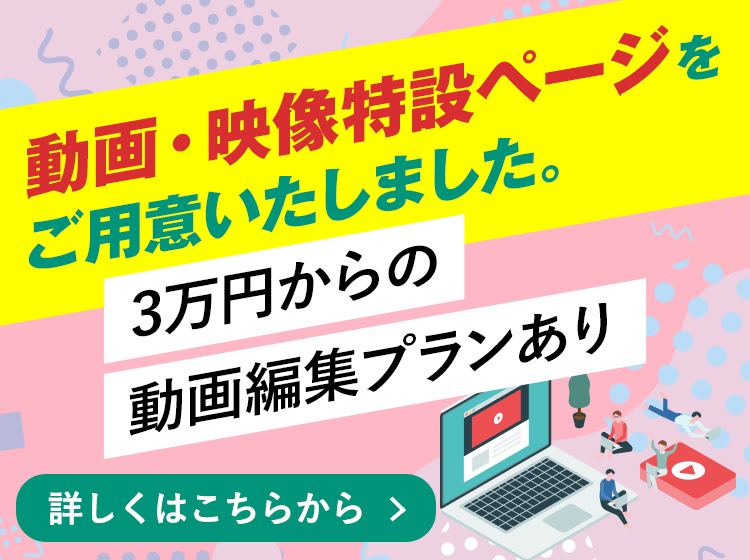見込み顧客が最終的に製品やサービスを選ぶとき、その決め手は何でしょうか。もちろん品質や機能、価格も重要です。しかし、情報が溢れる現代において、それだけでは「選ばれる理由」として弱くなっています。
多くの消費者は、論理的な機能説明よりも、「第三者によるリアルな推薦の声」や「作り手の人柄、製品開発に込めた熱い思い」といった情緒的な側面に心を動かされ、信頼を寄せるのです。
この「信頼」と「共感」を最も強力に伝える手段が「インタビュー動画」です。
インタビュー動画は、従来のテキストや静止画では伝えきれなかった企業の「顔」、社員の「熱意」、そして利用者の「表情や声のトーン」までも生々しく届けます。これにより、単なる導入実績の紹介を超え、説得力のある「ストーリー」として視聴者の記憶に深く刻まれるのです。
本記事では、「インタビュー動画の導入を検討している」「動画を作ったが、どう活用すれば良いか」と悩む企業担当者様へ、動画が必要不可欠な理由から、採用に必要な社員インタビューなど代表的な4つの種類と効果、制作のコツ、費用感、AI時代の考察まで徹底解説します。ぜひ本記事を参考にしてみてください。
【関連記事】
>効果的なナレーションとは?動画の出来を左右する「語り」を徹底解剖
>ブランディング動画を制作すべき理由とは?その重要性・必要性を解説
目次
1.インタビュー動画の必要性

企業PRに動画を活用するのが当たり前になった今、単に情報を伝えるだけでなく、「リアルな声」や「作り手の想い」といった「人間味」を伝えることの価値が高まっています。その最も効果的な手法が「インタビュー動画」です。
ここでは、なぜ今インタビュー動画が企業のブランディングや広報活動に不可欠なのか、その理由を解説していきます。
“顔が見える”信頼の構築
インタビュー動画は「人物×ストーリー×証拠」を同時に提供できるコンテンツです。顔の表情、声色、服装、所作、間合いといった非言語情報が詰まっていることで、視聴者にとっては、理屈とともに感情が働き、共感と信頼が醸成されます。
例えば、同じ言葉にしても、口コミサイトなどのテキスト情報のみと、満足そうな笑顔と熱のこもった口調で語るインタビュー動画とでは、どちらが心を動かされるでしょうか。
これは、ソーシャルプルーフ(社会的証明)と呼ばれるもので、人々が不確実な状況で、他者の行動や評価(例えば、第三者による具体的な証言)を参考にして、自らの意思決定を行うことです。このソーシャルプルーフを提示することは、見込み客の意思決定を後押しするために有効な手段となります。
採用・営業における絶大な効果
インタビュー動画はBtoC(消費者向け)で製品・サービスをPRするだけのものでなく、採用活動やBtoB(企業向け)の営業でも効果を発揮します。
近年の採用活動において、求職者は給与や待遇といった条件面だけでなく、その企業の社風や価値観、現場で働く社員の実際の人柄を、入社を決める上で強く重視する傾向にあります。
そのため、求職者にリアルな声や活動を伝えるため、社員インタビューや、複数の社員が集まって話す座談会などの導入が増えてきています。
また、BtoBの営業資料やFAQなどの代わりとして活用も可能です。導入している企業へのインタビューで「なぜ導入したのか」「どんな課題が解決したのか」を語ってもらうことで、商談時の会話効率が向上します。
共感が生まれる!SNSとの好相性
インタビュー動画は、SNSとの相性が非常に良いコンテンツです。なぜなら、SNSの利用動機の根底には「共感」や「発見」があるからです。
「人の顔が見える」動画の一部を再編集し、ショート動画としてXやInstagramのリール、TikTokで配信することで、視聴者の心を捉え、「いいね」や「シェア」といったエンゲージメントが格段に向上します。
ただし、ショート動画は縦型動画が基本となるため、インタビュー動画を撮影・編集する際にはSNSを活用することを前提として進めることをおすすめします。
さらに読む:人気の縦型動画
リスク低減と透明性の担保
企業目線で編集された広告とは異なり、インタビュー動画は「事実」と「人柄」が前面に出ます。
企業の代表者、社員、顧客といった「実在の人物」が、自らの「生の声」と表情で語ることで発信源が明確になり、いわゆる「広告」っぽさを抑えながらも、第三者の言葉が持つ高い説得力を生み出します。
このように透明性の高い情報開示は、視聴者(顧客や求職者)との信頼関係を構築します。そして、この信頼関係こそが、万が一ネガティブな事態が発生した際にも、企業へのダメージを最小限に抑える基盤となるのです。
2.【目的別】インタビュー動画の4つの種類とその効果

インタビュー動画といっても、その種類は多岐にわたります。「誰に何を伝え、どのような行動を起こしてほしいか」という目的をまず明確にしたうえで、どのような人をどのようなシチュエーションでインタビューするかで動画の種類が決まってきます。
ここでは代表的な4つの種類と、それぞれのポイントと効果を紹介します。
顧客の声・導入事例
「顧客の声・導入事例」動画は、BtoB企業にとって費用対効果が非常に高い最強の営業ツールです。製品導入を比較検討している担当者をターゲットに、既存顧客が自らの体験として「成果」を語ることで、見込み客の不安を解消し、導入を強力に後押しします。
また、BtoC(消費者向け)向けであっても、「リアルな体験談」や「生活の変化」に焦点を当てることで、製品・サービスへの共感や信頼感を醸成し、購入意欲を高めることができます。
ポイント
・導入前の「課題(Before)」が、導入後に「どう解決され、どんな具体的成果(After)」に繋がったかという変化のストーリーを明確にします。
・検討段階の視聴者が最も知りたい「なぜ他社でなく御社を選んだのか」という自社の競合優位性を明確にします。
・良い点だけでなく、導入時の苦労といったリアルなプロセスも誠実に語ることで、逆に顧客の信頼性を高めることができます。
効果
・検討段階の不安解消(導入ハードルの低下):他社の成功事例を見ることで、「自社でもうまくいくはずだ」という安心感を与え、導入決定への最後のハードルを越える後押しとなります。
・信頼性の飛躍的な向上:企業が自ら製品のメリットを語るよりも、実際に導入した顧客という「第三者のリアルな声」で語られるため、情報への客観性と信頼性が格段に高まります。
・導入後の具体的なイメージ促進:「導入前にどんな課題があったか」「どう活用して解決したか」というストーリーを通じて、検討中の顧客は自社に置き換えて導入後の成功イメージを具体的に描くことができます。
社長・役員メッセージ
企業の「顔」である経営トップが、自らの言葉で企業の存在意義(パーパス)や未来へのビジョン、大切にしている価値観などを語る動画です。
社内外のステークホルダー(社員、取引先、求職者)に向けて、ブランドイメージを構築していくことが重要です。
ポイント
・過去の実績や現在の業務内容を語るだけでなく、会社が「どこへ向かおうとしているのか」という未来の地図を示すことで、ステークホルダーに期待感と安心感を与えます。
・社長室など威厳のある雰囲気での撮影も良いのですが、社員とのふれあいや、現場に足を運んでいる様子などの映像を交えることで、企業の風通しの良さを伝えることができます。
・社員総会などの社内イベントで、経営方針やビジョンを共有するためにも効果的に使用できます。
効果
・企業ブランディングの強化:社長のメッセージは、視聴者に強い印象を与えます。これにより、企業の信頼性を高め、ポジティブなブランドイメージの構築に効果を発揮します。
・優秀な人材の採用促進:企業の理念をトップの生の声を通じて直接伝えることで、企業の魅力が深く伝わり、優秀な人材の採用に繋がります。
社員インタビュー
様々な部署、役職、キャリアの社員に登場してもらい、自らの言葉で仕事内容や社内の雰囲気など「働くリアル」を伝えます。特に採用活動において重要な役割を果たします。
ポイント
・「先輩社員の1日のスケジュール」を紹介するなど、具体的な業務の流れを語ってもらう動画は、求職者が入社後のイメージを具体的に想像しやすくなります。
・事前に用意した原稿をそのまま読むのではなく、社員のリアルで嘘のない、ありのままの声を届けることが重要です。
・社員インタビューには、一人が語る形式から、社員同士の対談・座談会形式まで、様々な種類があります。
効果
・入社後のミスマッチ防止:リアルな社内の様子や仕事内容を伝えることで、求職者の入社後のイメージギャップを減らし、ミスマッチを防ぐ効果があります。
・企業理解の促進:求職者が実際の社員の声を聞くことで、テキスト情報だけでは伝わりにくい社風や働き方への理解が深まります。
・「共感」と「親近感」を生み出す:年齢の近い社員が語るリアルな経験談や仕事への想いは、求職者にとって自分自身の姿を重ねやすく、この会社で自分が働く姿を具体的に想像する助けとなります。
座談会・対談形式
社員同士の座談会や対談、社長が外部の専門家などと対談する形式のインタビュー動画です。それぞれ役割や目的こそ異なりますが、一人で語るインタビュー動画に比べ、相手との掛け合いや会話の間、表情などがリアルに伝わり、視聴者を引き込みやすくなります。
ポイント
・キャスティング(出演者)は非常に重要です。社内の場合はテーマを語るのに最も相応しい社員を、外部の専門家を招く場合は業界内で尊敬を集める人物をアサインするなど、テーマに最適な人選を心がけましょう。
・参加者がリラックスして自由に意見を出し合えるように、使い慣れた社内会議室やデスクなど安心できる雰囲気づくりが大切です。
・対談のテーマ設定は、相手によって変えることが重要です。社員同士なら成功・失敗談などの本音を引き出す内容を、専門家相手なら業界の未来や最新技術など専門的な議論ができる内容を選びましょう。
効果
・視聴者を飽きさせない:複数人が参加して意見を交換するため、視覚的な変化の多さ、多様な意見など、様々な刺激があることで視聴者の集中力を維持させます。
・権威性・信頼性の構築:業界のオピニオンリーダーとの対談は、その業界における専門性や先進性を示し、企業の権威性を高めることができます。
・高価値なコンテンツ提供:視聴者にとって有益な専門情報を提供することで、見込み客やパートナー企業との関係性を強化します。
3.失敗しない!インタビュー動画の企画・制作 5つのステップ

インタビュー動画は、出演者に好き勝手に語ってもらったものを撮影して編集するといった単純なものではありません。
成果を出すためには、周到な「準備」と「設計」が重要です。ここでは、抑えておきたい5つのステップとして解説します。
ステップ1:目的(KGI/KPI)とターゲットの明確化
まずは制作に着手する前に、必ず「誰に・何のために」を言語化します。これはどの動画制作においても重要なステップです。
解像度高く設定することで、「どんな質問をすべきか」「どんな編集トーンにすべきか」が自ずと決まっていきます。
目的(KGI/KPIの設定)
たとえば、採用活動であれば、「採用サイトからのエントリー数を前年比120%(KGI)」にするために「採用エントリーボタンをクリック(KPI)」してもらうなど、なるべく数字で明確にしましょう。
ターゲット
なるべく具体的な人物像を描きましょう。たとえば、「都内の大学に通う、IT業界志望の就活生。安定志向より成長意欲が高い。」「中堅製造業の工場長。既存の生産ラインに課題を感じているが、DX導入には懐疑的。」など。
ステップ2:インタビュー対象者の選定と「本音」を引き出す質問設計
誰に話してもらうかは、動画の成否を分ける重要な要素です。社内であれ、外部の専門家であれ、テーマに沿って語れる人を選定します。
さらに、インタビューで語ってもらう質問はステップ1で定めた目的に応じた内容になるようにしましょう。
インタビュー対象者
導入事例であれば、導入に最も熱心だった現場担当者の方が、役員よりもリアルな言葉を持っていることが多々あります。採用動画であれば、視聴者が「自分もこうなりたい」と憧れを抱けるような、魅力的な社員を選定することが重要です。
インタビュー内容
「5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)」を基本に、インタビュー対象者の「感情」を深掘りする質問を用意することが望ましいです。たとえば、「導入の決め手は何ですか?」ではなく、「導入を決断する直前、最後に悩んでいた点と、それを払拭した決定打は何でしたか?」など。
ステップ3:撮影場所と機材の選定
続いては、撮影に関する内容を詰めていきましょう。インタビュー動画を見た視聴者が信頼できるクオリティを保つには、撮影の段取りが重要となります。
ロケーション
社長なら、ビジョンを象徴するような眺望の良い場所。社員なら、実際に働いているオフィス。開発者なら、ラボや工場の現場。その人らしさ、会社らしさが伝わる場所を選びます。
ライティングや音声などの機材
被写体を立体的に明るくさせるために専用の照明は必要です。オフィスの蛍光灯だけでは影ができ表情が暗くなりがちです。また、音声もカメラ内臓のマイクではなく、必ずピンマイクやガンマイクを使用し、クリアな音声を収録します。
さらに読む:撮影における注意点とは
ステップ4:撮影当日のディレクションと「場の空気づくり」
どんなに準備をしても、撮影当日のインタビュー対象者が緊張していては良い話を引き出せません。撮影に参加する企業担当者、ディレクター、カメラマンなど関係者全員が協力して話しやすい雰囲気を作っていく必要があります。
ディレクション
ディレクターは、撮影中に「今のエピソード、もう少し具体的に聞けますか?」「すごく良い表情でした!」と、客観的な視点からインタビュアーやインタビュイーを導きます。
リアルな対話
事前に決めた質問を上から順に読み上げるのは最悪です。インタビュアーは相手の話に深く頷き、相槌を打ち、「それはつまり、どういうことですか?」と深掘りし、対話のキャッチボールを行います。
ステップ5:編集で「ストーリー」を構築する
撮影後、最後の仕上げとして「編集(ポストプロダクション)」作業に移ります。撮影したままの素材には、不要な「間」や言い淀み、話の重複部分などが多く含まれています。視聴者にとって見づらい点を解消し、動画のクオリティを高めて「伝わる」映像にする必要があります。
「ストーリー」の構築
撮影した全ての素材を見返し、「目的」に沿って、どの発言を使い、どの順番で並べるかを構成します。視聴者の感情が動くような「起承転結」を意識します。
違和感無く見てもらえる動画
「えー」「あのー」といった不要な間のカット、テロップの挿入、雰囲気を演出するBGM、関連する「インサートカット」(補足映像)の挿入などで視聴者は飽きずに内容を理解しやすくなります。
さらに読む:出来栄えを左右する編集
4.インタビュー動画作成でかかる費用

インタビュー動画の制作費用は自社の内製で行うか、動画・映像制作会社に依頼するかで大きく異なります。
ここでは、それぞれのメリット・デメリットを紐解きながら、費用相場を比較していきましょう。
自社で撮影・編集する場合
企業のプロモーション動画やブランディング動画、動画広告などに比べて、撮影や編集における難易度は比較的低いでしょう。ただし、しっかりと自社の魅力を伝えるためには、撮影のための機材やある程度の編集経験が必要となります。
メリット
・コスト削減:制作会社への外注費を大幅に削減できる点が最大のメリットです。
・柔軟性:社内の都合に合わせて撮影スケジュールを組め、修正や変更にも迅速かつ柔軟に対応できます。
・ノウハウの蓄積:制作の経験を重ねることで、撮影や編集のノウハウが社内に蓄積されます。
デメリット
・社内リソースの負担:企画、撮影、編集といった一連の作業に、社内のリソースを割く必要があります。
・クオリティの担保が難しい:撮影や編集の専門知識がない場合、音声が聞き取りにくい、映像が暗い、編集が雑になるなど、プロ品質の動画を作るのは困難です。
・機材・環境の準備:撮影に必要なカメラ、マイク、照明機材や、編集用のPC・ソフトなど、制作環境を自社で整える必要があります。
動画・映像制作会社に依頼する場合
インタビュー動画をはじめとした様々なジャンルの動画を制作しているため、動画制作に関する知識や技術は十分にあります。さらにプロならではの様々なサポートやアドバイスなども力になってくれるでしょう。
メリット
・高品質:最大のメリットは、高いクオリティが期待できることです。視聴者に信頼感を与えるプロ品質の動画に仕上がります。
・社内リソースの節約:企画、撮影、編集といった時間のかかる作業を一任できるため、自社の担当者は本来の業務に集中できます。
・企画・制作のノウハウ:どのようにインタビューすれば企業の魅力が伝わるか、どのような構成にすれば視聴者を惹きつけられるかといった、成果を出すためのノウハウを持っています。
デメリット
・制作コスト:自社制作に比べて、費用は高額になります。撮影にかかる人やカメラの台数などによって変動があります。
・コミュニケーションコスト:制作会社とイメージをすり合わせるための打ち合わせや、修正依頼などのやり取りが発生します。
さらに読む:失敗しない制作会社の選び方
自社制作(内製)と動画・映像制作会社(外注)の費用の比較
それでは費用相場の比較を見てみましょう。自社で内製するより動画・映像制作会社に依頼する方が高くなりますが、内容によって費用に幅があります。
| 費用 | 制作のポイント | |
| 自社制作 | 低コスト (機材費・編集ソフト代・社内人件費のみ) | 撮影は自社で、編集はプロに依頼など、役割を分担して行うことで、費用を抑えつつ、プロ並みの仕上がりも可能です。 |
| 動画・映像制作会社 | 10万程度 撮影が1名・短時間で、編集もカットとテロップ挿入のみといったシンプルな構成の場合です。 | 目的に応じてどこまでのクオリティが必要になるのかプロに相談してみましょう。たとえば、新卒採用のために親近感を演出した場合、あえてスマホで撮影しリアルな表情や所作を映し出すなども一つの手段となります。 |
| 50万程度 プロによる企画構成、複数台のカメラでの撮影、インサートカットの追加、BGM・ナレーション挿入など、プロ品質を求める場合の相場です。 | ||
| 100万以上 著名人をアサインした対談動画や複数拠点での撮影などを行うと高額になります。 |
さらに読む:動画制作費を徹底解説!
5.AI時代のインタビュー動画の未来

ここまではインタビュー動画の「現在」の活用法について解説してきました。最後に、インタビュー動画が「未来」においてどのような役割を担うのか、独自の視点をお話しします。
AI時代にインタビュー動画は必要なのか
AI時代に突入している現在、インタビュー動画の周辺環境はどのような変化を遂げていくのでしょうか。
結論からいうと、「インタビュー動画はAI時代により必要なコンテンツとして重宝される」と言えるでしょう。
生成AIが進化し、テキストやリアルな画像・動画まで自動生成できる時代になりました。いっぽう、世の中が「AIによって生成されたコンテンツ」で溢れかえると、誰が本物なのか、どれが正しいのかの判断が難しくなります。
「顔」と「実名」を出し、自らの「声」で語るインタビュー動画は、「信頼性の最終的な担保」として、その価値が相対的に高まっていきます。AIが生成した「平均的で正しい答え」や「平均的な人間」ではなく、「誰が何をどのように発言した言葉」こそがこれからの時代に求められるコンテンツになります。
AIに選ばれるインタビュー動画
Googleなどの検索エンジンは、今、生成AIを活用した「AI Overview(AIによる要約)」を検索結果の上部に表示するようになっています。ユーザーは、もはや個別のウェブサイトをクリックせず、AIが要約した答えだけで満足する時代が来ようとしています。
では、AIはどのような情報を「信頼できる情報源」として引用し、要約の材料にするのでしょうか?
それは、「E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)」が確立されたコンテンツです。AIは、匿名の誰かが書いたブログ記事よりも、「その分野の専門家が実名で語っている内容」や「企業の公式な見解として経営者が語っている内容」を優先的に参照します。
つまり、誰の発言であるか、その発言が専門的で、一次情報(本人の経験)に基づいているか、を正確な文字起こしを行い、ウェブサイトなどに掲載することで、AIによる要約(AI Overview)の「引用元」として選ばれる可能性が高まるのです。
まとめ:インタビュー動画で信頼感と共感を呼び込み、選ばれる企業を目指そう!
ここまでの解説を通じて、インタビュー動画がもたらす効果や成功へと導くステップなどをご理解いただけたでしょうか。
「インタビュー動画」が、単なるプロモーションの域を超え、企業の「信頼」を可視化し、採用を成功に導き、さらにはAI時代の戦略的資産にまでなり得ることを、本記事でお伝えできていれば幸いです。
インタビュー動画は他の動画ジャンルに比べると、比較的容易に導入が可能です。最初はスマートフォンで撮影した短めの社員メッセージなどでも、視聴者に届けることで共感を得られるかもしれません。
その際は、ぜひ「3.失敗しない!インタビュー動画の企画・制作 5つのステップ」で解説した内容を参考にしてみてください。
大切なのは、自社の社員や顧客のリアルな生の声を外に届けることです。それは決して他社やAIが真似できない最強のコンテンツとなるはずです。
ぜひ本記事を参考にして、信頼感と共感を得るためにインタビュー動画を顧客に届けてみてはいかがでしょうか。
バドインターナショナルは、社員やTOPインタビュー、座談会などのインタビュー動画全般に対応可能です。弊社のカメラマンとインタビュアーが、企画から撮影までをサポートを行うことで、ターゲットの心に響くストーリーを構築します。 また自社スタジオも完備してますので、ご活用ください。