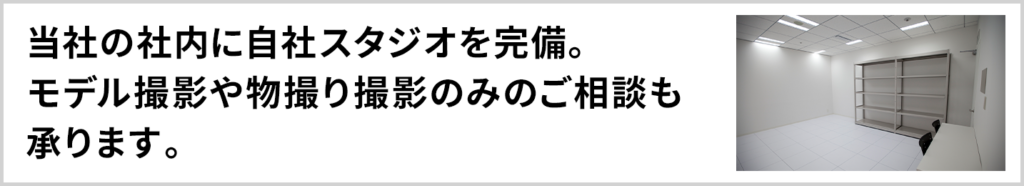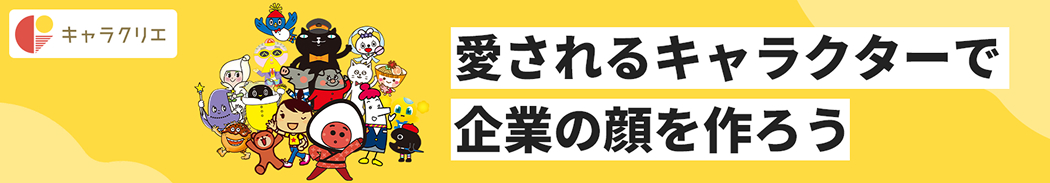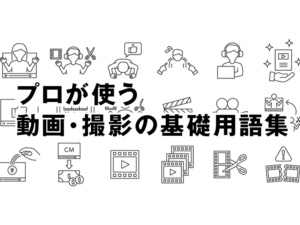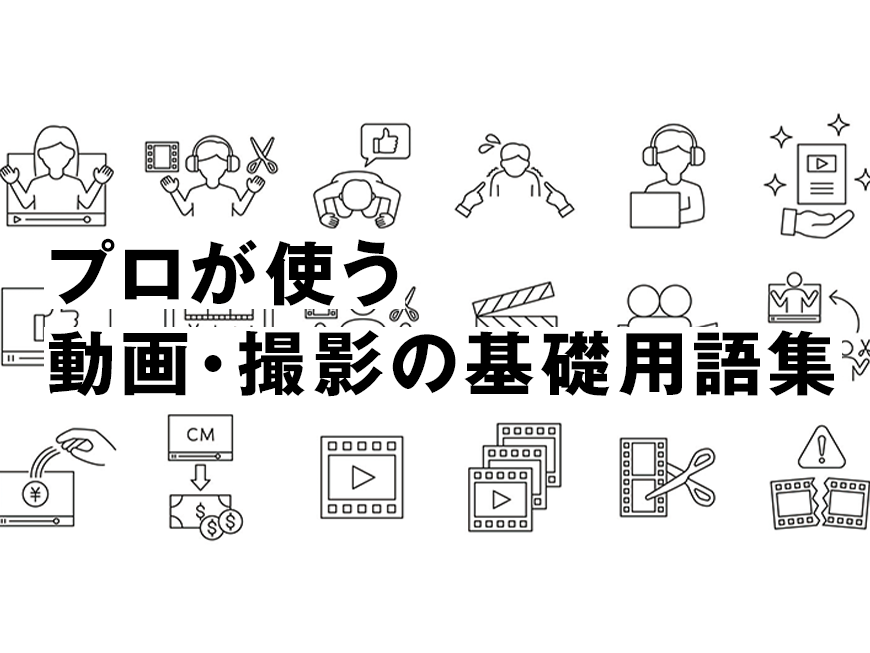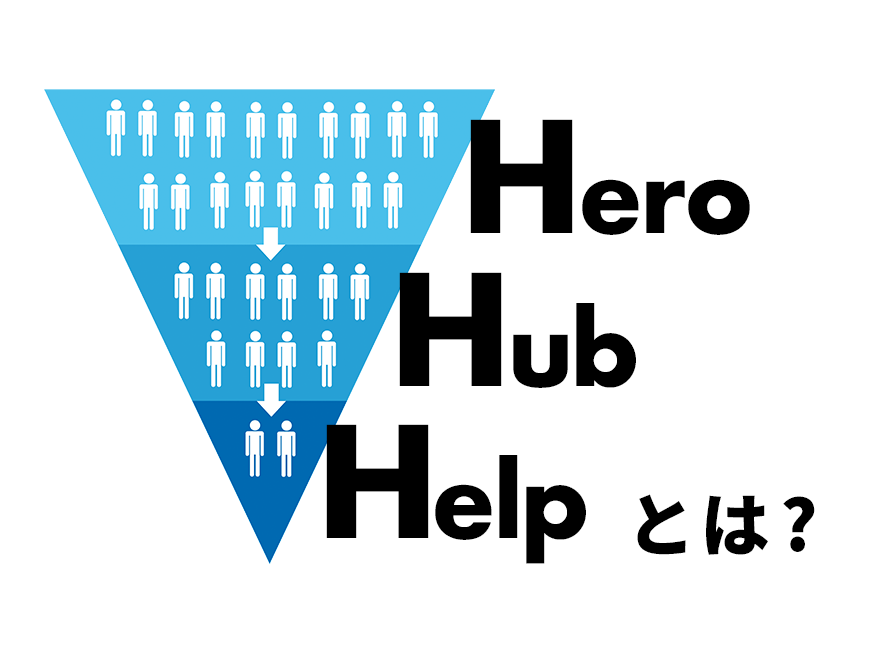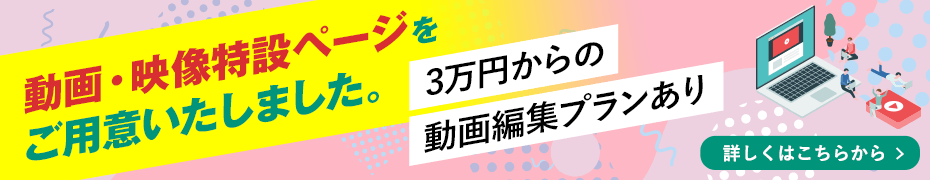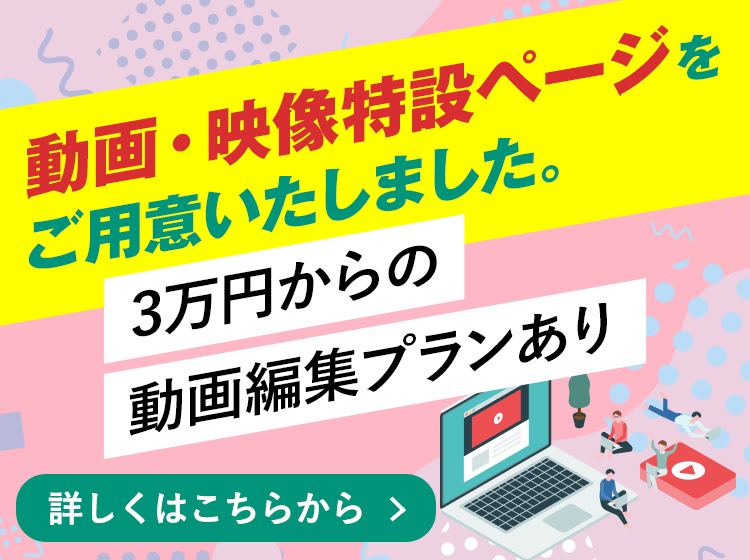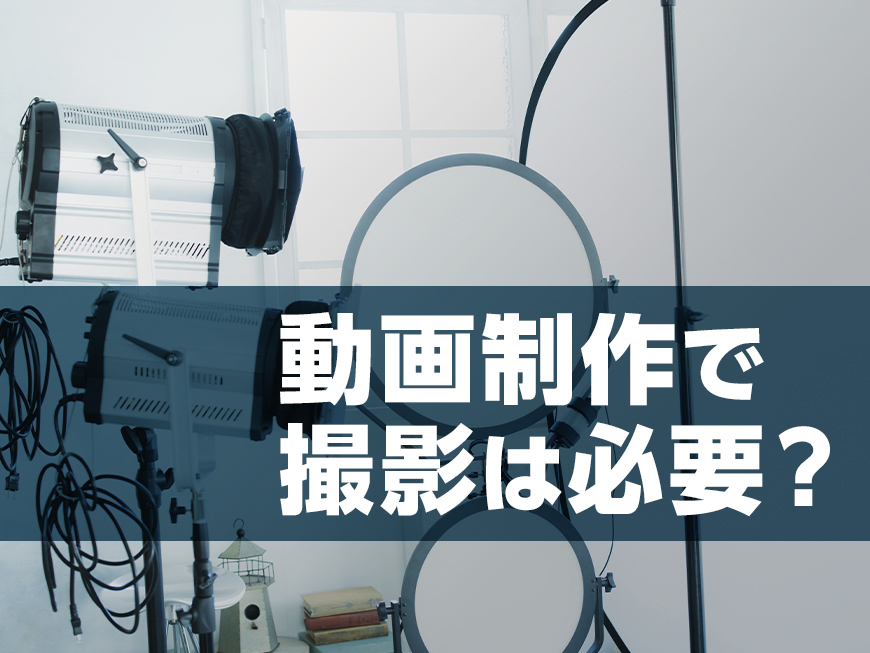
動画制作を検討している企業の皆様にとって、実際の「撮影」という工程を含む動画制作は魅力的な選択肢である一方、撮影にかかる費用や手間といった部分への懸念や不安もあるのではないでしょうか。
動画の撮影と聞くと、テレビ番組や映画のような、大規模な撮影シーンをイメージする方もいらっしゃるかもしれません。しかし一企業が制作するプロモーション動画や採用動画などの撮影は、一般的にもっと小規模に行われるものです。
そこで本コラムでは、実際の撮影を必要とする動画の種類や費用感について説明するとともに、メリット・デメリット、注意すべき点についてもわかりやすく解説します。また、撮影なしで制作できる動画についても触れておきたいと思います。
自社で撮影を伴う動画を制作する際の参考に、そして予算策定の際の一助になれば幸いです。
【関連記事】
>【事例付き】動画制作にかかる費用の相場は?ジャンル別や内訳別でわかりやすく解説!
>動画制作会社の見積書を大公開!各項目と費用を抑えるコツを徹底解説
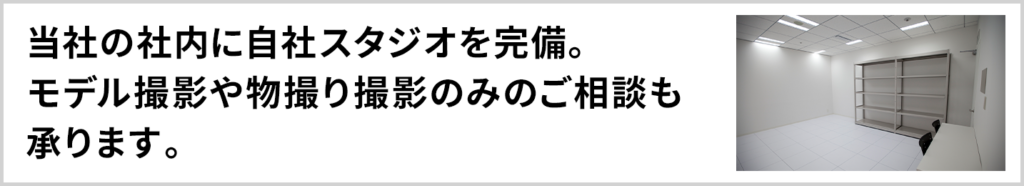
目次
1.「撮影有り」の動画のメリット・デメリット

動画制作の際、実際に撮影を行うべきかどうかは、その動画の目的や表現したい内容によって変わってきます。
実写なら登場人物の表情や動き、製品の色味や質感などがリアルに捉えられるので、視聴者の共感や信頼を得たい時には、非常に有効な手法だと言えるでしょう。
それでは実際に撮影して制作した動画には、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。
「撮影あり」動画の5つのメリット
リアリティのある動画が実現する
現実に存在する人物や物を撮影するため、商品やサービスの魅力をリアルに、具体的に伝えられる。
視聴者の共感を得られる
実在の人物が登場することで、視聴者が内容を自分に置き換えて共感し、感情移入しやすくなる。
視覚的な訴求力が期待できる
文字や静止画だけでは伝わりにくい情報も、実際の人物や製品が動画の中に登場し、表情や質感、動き、音声などを伴って再生されることで、より訴求力が強まり効果的に伝えられる。
信頼性の向上が望める
実際に存在する店舗や従業員を動画の中で紹介すれば、視聴者に安心感を与え、商品やサービスへの信頼性の向上に繋がる。
撮影した映像は素材としても活用できる
製品やオフィス・店舗の様子などを実際に撮影した映像は、素材として商品紹介や会社紹介をはじめ、採用活動やイベント告知など、様々な動画で再利用ができる。
「撮影あり」動画の4つのデメリット
コストがかかる
出演者の起用や撮影場所の確保、機材の準備などにどうしても費用がかかってしまう。
手間と時間が無視できない
準備や実際の撮影、撮影後の編集作業など、完成までに多くの手間と時間がかかる。
クオリティの担保が求められる
誰でも簡単に動画撮影ができる時代だが、完成した動画にある程度のクオリティを確保しないと、視聴者の離脱を招き、逆効果になる可能性がある。
差し替えや修正が難しい
撮影後に出演者や内容の変更・修正が必要になった場合、その部分だけを差し替えることは困難で、一から撮り直す必要がある。
2.「撮影なし」の場合の代替案

コスト面やスケジュール面で撮影が難しい場合でも、特定の情報を効率的に伝えるための動画作成は可能です。ここでは実際の撮影なしで制作できる主な動画の種類と、それぞれの特徴を解説していきます。
アニメーション動画を検討する
アニメーション動画なら、実写では表現しにくい抽象的な概念やプロセスを、視覚的にわかりやすく解説することが可能です。また、独自のキャラクターを用いることで、親しみやすさも演出できます。
出演者や撮影場所、機材などの準備が不要なため、制作の自由度が高いのが、アニメーション動画の大きなメリットです。
さらに読む:【事例付き】10種類のアニメーション動画
既存の素材を使用する
自社で所有している静止画や動画を使ったり、素材サイトなどで素材を入手したりすることで、費用や手間を抑えられる場合があります。
ただし、あちこちから集めた素材を継ぎ合わせて作った動画は、全体を通してチグハグな印象になってしまう可能性も。
既存の素材を活用する場合は、著作権の所在を確認すること、そしてクオリティの維持に注力することが必要です。
生成AIを活用する
最近は生成AIが作り出す動画も、目覚ましい進化を見せています。コスト削減や時間短縮に繋がるなど、生成AIの活用には良い面があるのも事実です。
しかし生成AIはまだまだ発展途上のため、人間が作るような緻密で繊細な表現は難しく、意図したような動画にならないことも。思い通りの映像ができるまで何度も生成を繰り返すうちに、コストや時間が予想外にかかってしまうケースもあり得ます。
また、生成された動画の商用利用に関する規約が不明確であったり、著作権侵害の可能性が出てきたりする場合もあるため、現段階では生成AIの利用には注意が必要だと言えるでしょう。
3.撮影を伴う動画が向いているジャンル

企業が動画を制作する目的は多岐にわたります。そのすべての動画において、実写での撮影が効果的というわけではありません。
ですが視聴者に情報をわかりやすく伝えるために、やはり実際の撮影を行うほうが向いているジャンルも確かに存在します。ここでは実写による撮影が効果的な動画のジャンルを、4つご紹介していきましょう。
商品紹介動画
製品が現物として存在する場合には、実際にその製品の撮影をすることで、質感や使用感を視聴者にリアルに伝えられます。それにより商品の特徴や利用シーンを、具体的にイメージしてもらいやすくなるのです。
また、動画で商品そのものを見てもらえれば、「買ってみたら思っていたイメージと違っていた」という、視聴者のネガティブな反応を防ぐことにも繋がります。
新製品のプロモーション動画や使い方動画などは、実写の効果が最大限に活かされるジャンルだと言えるでしょう。
会社紹介・採用動画
オフィスの日常風景や従業員の毎日の様子を映し出すことで、企業の雰囲気がより具体的に視聴者に伝わります。
実際に撮影された、社員が日々の業務をこなす姿や彼らへのインタビューを通して、求職者は入社後のイメージを掴みやすくなるのです。
小型ドローンを使った撮影も、こういった動画には有効です。会社や工場の外観や設備を紹介したり、オフィスツアーを行ったりといった動画も、インパクトのある映像に仕上がります。
さらに読む:ドローン空撮の魅力
お客様の声・インタビュー動画
実写で顧客や従業員のリアルな声を届けられれば、商品・サービスの信頼性や企業イメージの向上に大きく貢献するでしょう。
特に顧客へのインタビューを撮影した動画は、商品紹介やお客様事例、採用活動など幅広い用途で活用できます。
イベント・セミナー動画
イベントやセミナーなどの会場の臨場感を伝え、参加者の熱意や内容の濃さを記録する動画です。
これは実際の撮影以外では表現できない動画であり、イベントの記録としてはもちろん、ハイライト映像としての使い方も可能です。
こういった動画は、当日参加できなかった人への情報共有や、次回の集客にも繋がる重要なコンテンツとなり得ます。
4.動画撮影時の注意点

実写の撮影となると、出演者やカメラマン、撮影場所の手配、撮影自体の準備、スケジュールの調整など、動画制作に必要な工数やリソースも増えていきます。
また「せっかく撮影したものの、目指していた映像にならなかった」という事態が起きないよう、万全の態勢で臨まなければなりません。
そのためには撮影までの綿密な段取りや撮影当日の流れ、問題が発生した際の対策など、様々な状況に対応していくという、ハードルの高い業務をこなす必要があります。
コストやスケジュールを考えると、撮り直しは絶対に避けたいもの。そのためにも以下の点に注意して、実際の撮影に挑みましょう。
きちんとした企画・構成案を準備する
「何をどう撮影したいのか」という目的を明確にし、事前にしっかりした絵コンテや構成案を作成することが重要です。その際、「香盤表(こうばんひょう)」と呼ばれるスケジュール表も、あらかじめ準備しておきましょう。
香盤表とはキャストの動きや撮影時間、出演する順番や移動時間をはじめ、衣装や小道具などの情報も詳細に記載されたスケジュール表で、撮影を円滑に進める上で必要不可欠な資料です。
また撮影の規模によっては、カメラ・照明・音声といった機材の準備や、関係する撮影スタッフの手配も必要です。
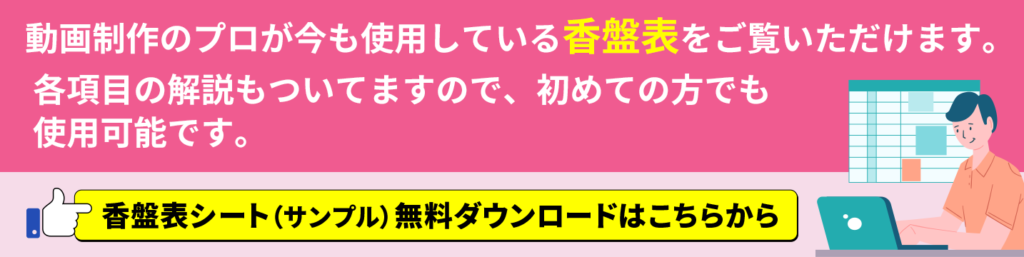
事前にロケーションを選定する
実写の場合は、その撮影場所も非常に重要な要素です。どこで撮影しても良いというわけではありません。
社員へのインタビュー動画など、自社内を撮影場所として利用する場合はともかく、屋外で撮影を行う場合は許可取りが必要になるケースもあります。
ロケーションの選定は、許可取りやスタジオを借りる際にかかる費用など、制作コストにも関わってくる問題です。どのような場所で撮影するのかを、企画・構成の段階でしっかりと決めておきましょう。
出演者がいる場合は早めに押さえる
モデルやタレントなどに出演を依頼する場合は、出演交渉やスケジュール調整が必須です。自社で直接交渉する方法もありますが、これまでにプロのモデルを起用した経験がない場合、少々ハードルが高いかもしれません。
その場合はキャスティング会社に交渉や手続きの代行を依頼したり、サブスクサービスを利用したりといった方法も選択肢に入れておきましょう。
こちらの撮影希望日とスケジュールが合わなかったり、動画のイメージに合ったモデルやタレントが手配できなかったりする事態もあり得ます。実写での撮影が決まったら、できるだけ早めに手配しておくことをおすすめします。
天候に左右される可能性を考慮しておく
屋外で撮影する場合、撮影当日の天候でスケジュールが左右される可能性があります。そのためスケジュールを作る段階で、撮影の予備日を複数設けておくことが重要です。
どの程度までの天候なら許容範囲なのかを事前にスタッフ間で話し合い、当日撮影を決行するかどうか決定しましょう。
5.撮影を伴う動画制作にかかるコスト

撮影を伴う動画制作にかかる費用は、企画の内容や撮影日数、出演者の有無、使用する機材、そして編集の手法など、撮影の規模によって大きく変動します。
例えば、カメラマン1名で社内のみで行う撮影と、屋外でロケハンを行い、カメラマンやヘアメイク、スタイリストなど複数のスタッフが関わる撮影では、その費用に数百万円の差が出ることも。
一般的に採用動画や製品PR動画の制作で、TOPインタビューや開発者インタビューを行う場合、あるいは実写で企業や製品紹介の動画を作る場合は、およそ20万〜100万円程度の制作費がかかります。
費用を抑えたい場合には、まず企画の段階で予算を明確にし、撮影に必要な要素とそうでない要素を洗い出すことが重要です。
また、撮影を行わず、既存の素材のみを使って動画を制作することも可能ですので、詳しくはプロの動画制作会社に相談してみましょう。
まとめ:実際に撮影した動画ならではの魅力的な表現を活かそう
今回は動画制作において、実際に撮影することのメリットやデメリット、その注意点をご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。
一口に「撮影」と言っても、小規模のものから大規模なものまで、その内容は様々です。実写の場合はどうしても関わる人数が多くなるため、手間やコストがかかってしまうのは仕方のないことかもしれません。
とは言え、実際に撮影して作った動画には「リアリティのある映像」という大きな特色があり、視聴者にも内容をより身近に感じてもらえるはずです。
イラストを使ったアニメーション動画や動画素材サービスを利用した動画とは、ひと味もふた味も違う魅力があり、視聴者への浸透力といったメリットも期待できます。
実写動画を制作するには、その工程で多岐にわたる調整が必要となってくるため、プロの動画制作会社に相談することをおすすめします。
バドインターナショナルには、プロのカメラマンが社員として在籍していますので、スケジュールやコスト面で柔軟に対応が可能です。
撮影の規模にかかわらず、企画やロケ地の選定、出演者のキャスティングなど、撮影・動画制作に関わる全ての工程を一括で承ります。ぜひお気軽にご相談くださいませ。